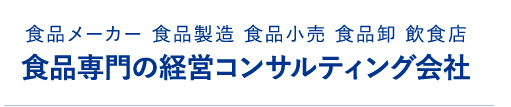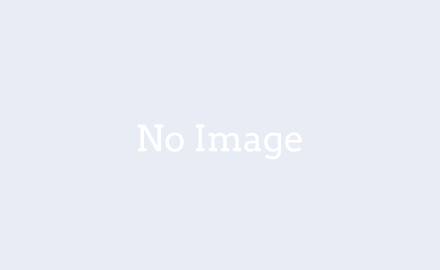2025.04.25UP
【精肉店の勝ち残り戦略】中小企業経営に迫る「2つの”2029年問題”」とは?|食肉業界専門経営コンサルタントのブログ(2025.04.25)
目次
2つの「2029年問題」に備える。“人が減る”と“企業が選ばれなくなる”時代へ
物流問題を指した「2024年問題」は非常に有名でしたが、みなさまは「2029年問題」というのはご存知でしょうか?
企業によっては2024年問題以上に、経営に直接的なダメージを受けることになる、非常に大きな問題です。
実は中小企業・小売・サービス業にとって大きな転機となる2つの課題が、確実にその年を起点として表面化してきます。
本日はその「2029年問題」に関するわかりやすい解説と、その対応についての案内を目指します。
2029年問題(その①):団塊ジュニアの定年接近による人材喪失
まず1つ目の2029年問題は、かねてより注目されている労働人口の急減問題です。
1971〜1974年生まれの団塊ジュニア世代が2029年には全員55歳を超え、中堅・ベテラン層が大量に退職フェーズに入ります。
これにより、中小食肉企業では特に以下のような懸念が生じます。
✅ 精肉業界で特に影響するのは:
-
カット技術・惣菜レシピなどの属人的なノウハウが失われるリスク
-
現場の安定感や売場マネジメント能力を持つスタッフがごっそり抜けるリスク
これにより、ただでさえ人が足りない現場が、
“技術も運営力も消える”二重苦の時代に突入するといった懸念が、具体的な課題として表層化してくるタイミングとなると考えられます。
2029年問題(その②):「デジタル世代」が社会に出てくる最初の年
もう1つの2029年問題は、採用市場の“選ばれる側の条件”が大きく変わるという点です。
2025年から大学入試の共通テストに「情報Ⅰ」が追加され、
全ての新入生がプログラミング・データリテラシー・情報社会の基礎理解を問われるようになりました。
つまり2029年に社会に出てくる新卒世代は、「デジタルに明るいことが“標準スキル”の世代」なのです。
これにより、中小食肉企業では特に以下のような懸念が生じます。
✅ デジタル非対応企業は「時代遅れ」に見えるリスク
-
レジが手打ち
-
紙の出退勤表やFAXでの受発注
-
SNSやLINEが機能していない
-
キャッシュレス非対応
- ネットショップ等デジタル販売部門がない
このような職場環境では、「ここで働くと将来に活かせるスキルが身につかない」と見なされやすくなり、
若手から“選ばれない会社”になってしまう恐れが、今以上に高まることになると考えられます。
すでに全国で生じている「少子高齢化」ですが、一部企業では海外人材や若手人材の確保のための動きを強化しており、世の中で言われているほど労働力不足に悩まされているわけではない、といった状況が生まれています。
「少子高齢化だから仕方がない」のではなく、
「わかっていたのに何もしない企業」は沈んでいき、事前に対応をしている企業は残っていく、ということになるでしょう。
2つの2029年問題をまとめると…
| 項目 | 問題の内容 | 精肉店への影響 |
|---|---|---|
| 【①】人材の喪失 | 団塊ジュニア世代の大量退職による“技能・運営力の空洞化” | 技術・売場のノウハウ消失。教育・引き継ぎ不足で現場崩壊の危機 |
| 【②】企業の魅力低下 | 情報教育を受けた“デジタルネイティブ世代”が非デジタル企業を敬遠 | 採用応募数が激減。若手が来ても定着しない構造が加速 |
今から打てる現実的な3つの対策
✅ ① 技術と接客のマニュアル化(属人化の解除)
-
カット技術、盛り付けの基準、声かけの言い回しなどを動画・手順書で見える化
-
退職前に“引き継ぎ資産”をつくり、知識のバトンをつなぐ仕組みを整備
公益財団法人日本食肉流通センターが、コマーシャル規格に関するわかりやすい動画を作成してYoutubeで発信してくれています。
意外なことに、チャンネル登録者数は今日時点で281人と非常に少ないですが、
こうした動画を自社で作成するのは非常に労力がかかりますし、厳しく管理されている部位規格の説明を自社独自で作成する意義もほぼないでしょうから、積極的に視聴を促すことをおすすめします。
Youtubeリンク:https://www.youtube.com/channel/UCbGkcoZBnqS2yE5RP9vZJhA
✅ ② 働く人に“選ばれる会社”になるブランディング
-
自社HPやGoogleMAPに「スタッフの声」や「働く姿」を掲載
-
「手書きメモ文化」から「チャットツール」への移行など、小さなデジタル化を見える形で導入
-
LINE公式やモバイルオーダー活用など、“顧客対応に強い店=若手が活躍できる店”を演出
半年ほど前にある会社で、「社内のすべての情報共有をLINEワークスに一本化する」という事を推進しました。
従業員の業務カレンダー、業務日報の提出、日々の報連相、ファイル/資料の共有・・・etc
混乱したり手こずったのは経営層だけで、
アルバイトスタッフも含めて若手人材はすんなりとそうした変化に対応できています。
こうした点でも、「経営者こそ変わる覚悟」を持たなければいけません。
✅ ③ “デジタル人材活用業務・事業・ポジション”の整備
-
事務や総務面では、POSやシフト管理アプリ、クラウド会計ソフトなどの導入 → 勤怠・売上分析・棚割管理の見える化は必須でしょう
-
小売営業面では、LINEやMAツールなどを活用したプログラム型販促や、EC事業の運営なども重要ですね
- 卸営業面でも、BtoB-ECの発足や、TANOMUのようなLINEで発注を受ける仕組みの導入なども進めておきたいところです
すでに我々の関係先では、
BtoC-EC事業の新規立ち上げ&育成を進めており、2029年以降に現れる新世代が働きたいと思えるようなポジションを構築しておくと共に、そうした人材をマネジメントできる先輩社員のデジタルマーケティング力育成を推進していますし、
BtoBについても前述したTANOMUの導入企業も増加してきました。
もう待ったなしです。今年を変革元年にしましょう。
「人が減る」だけでなく、「来たがらない」――
それが2029年問題の本質です。
✅ 技術は奪われる前に“仕組み”に落とし込む
✅ 若手に選ばれる環境を“少しずつ整える”
✅ 目の前の人手不足と、5年後の“無応募時代”に備える戦略を
未来を恐れるのではなく、“見える未来”に対して今から動く勇気を持ちましょう。