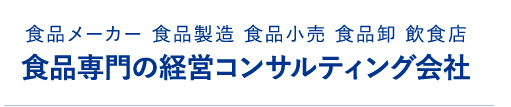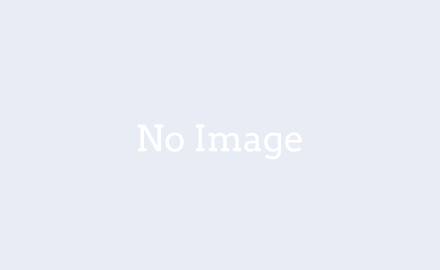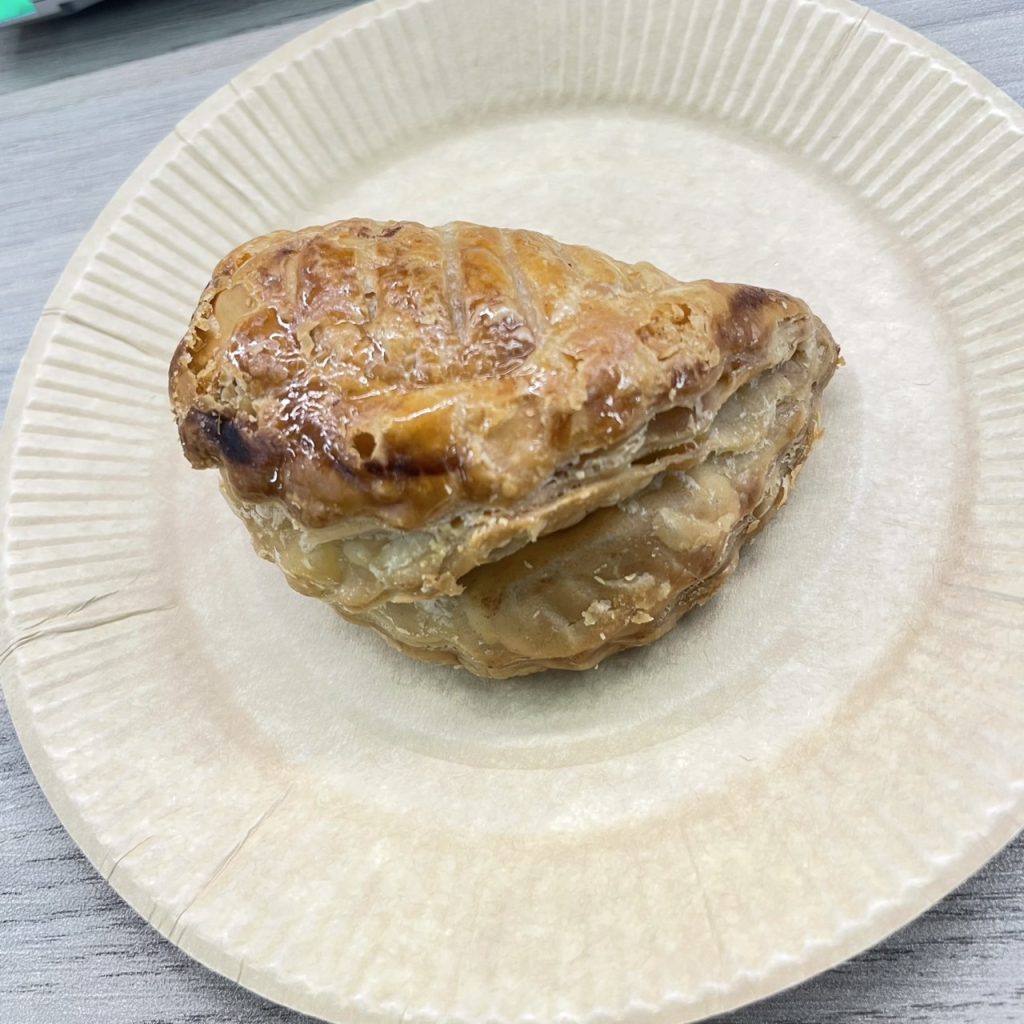2025.07.03UP
令和6年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書の解説
こんにちは、中口聡明です。
今回は総務省が発表した最新の「情報メディアの利用実態調査」をもとに、ネットショップ運営に関わる方が注目すべきポイントを整理してお届けします。
https://www.soumu.go.jp/main_content/001017240.pdf
1. インターネットが情報接触の主軸に
インターネットの平均利用時間は平日181.8分、休日183.7分と、リアルタイムのテレビ視聴(平日143.4分、休日161.4分)を全年代で上回った。
40代以上でもネット利用がテレビを上回る傾向が強まり、情報メディアの主軸が完全にインターネットへと移行したと言える。
食品業界においても、従来型のマスメディア依存から脱却し、デジタル空間を前提とした情報発信の再構築が急務となっている。
2. SNS利用の多層化と機能分化
SNSの利用率は、LINE(91.1%)、YouTube(80.8%)、Instagram(52.6%)、X(43.3%)が上位を占めた。10代ではTikTokの利用が65.7%に達し、Z世代を中心に視覚・動画重視の傾向が鮮明である。
メディア接触の分散が進む中で、各世代・目的に応じたチャネル最適化が必須となる。
-
LINE:全世代型・CRM(クーポン、リマインド、接客)
-
Instagram・TikTok:Z世代向け商品訴求
-
YouTube:調理動画、生産者ストーリーの可視化
3. 「信頼」と「速報性」の分断構造
調査によると、速報性においてはネット(54.4%)、信頼性ではテレビ(51.6%)、新聞(59.9%)が高評価を得ている。
すなわち、企業がネット上で発信する情報は、スピードだけでなく「信頼性の担保」が極めて重要であることを示す。
食品企業は、産地情報、製造工程、品質検査結果、ユーザーのレビュー等を積極的に公開することで、ネット情報の“信頼性のギャップ”を埋める取り組みが求められる。
4. 「ながら視聴」時代への対応
20〜30代を中心に、「テレビ視聴とスマホ利用を同時に行う」ながら視聴が定着。特に19時〜22時の時間帯は複数スクリーンを跨いだ情報接触が集中する。
この時間帯に、SNS広告、インフルエンサー発信、ライブコマースなどを仕掛けることで、認知効果を最大化できる。
5. 中小食品企業が取るべき情報戦略
(1)SNSと動画の重点活用
-
製品特徴やこだわりの製法を、短尺動画で可視化
-
商品開発の背景、生産者の思いなど“ストーリー”の訴求
(2)LINEの活用による関係構築
-
クーポン配信、再購入リマインド、在庫情報などを自動化
-
高齢層のスマホ利用拡大に伴い、重要な接点チャネルに
(3)信頼性あるECサイト整備
-
第三者評価の明示、FAQ整備、配送ポリシーの明文化
-
「食品=安全性・信頼性が第一」であるという基本に忠実な構成
(4)世代別メディア特性への対応
-
若年層:映像中心、共感訴求
-
中年層:機能性と誠実な情報提供
-
高齢層:使いやすさと丁寧なフォロー体制
カテゴリー
- ToB(1)
- ギフト(6)
- キャッチコピー(1)
- クロスセル(1)
- コーポレートギフト(1)
- ダイレクトリクルーティング(1)
- タッチポイント(2)
- ビジネスマン(2)
- ビジネスモデル(1)
- ヒット商品(1)
- ライフサイクル(1)
- 人件費・採用コスト高騰(1)
- 仕組み化(1)
- 価格設定(1)
- 個別対応(1)
- 入口商品(1)
- 写真(1)
- 効率化(2)
- 原理原則(4)
- 名簿ビジネス(1)
- 商品力(15)
- 因数分解(1)
- 固定化力(4)
- 売上アップ(1)
- 売場力(12)
- 季節指数(2)
- 実店舗の活用(1)
- 客単価アップ(2)
- 店舗コンセプト(1)
- 成長期(1)
- 戦略(1)
- 採用(1)
- 接客力(9)
- 新媒体(1)
- 業務効率化(1)
- 決算情報(4)
- 洋食(1)
- 立ち食いそば・うどん(1)
- 蕎麦(1)
- 計画(1)
- 通年ギフト(2)
- 通販事業(0)
- 選べれる理由(1)
- 都市型(2)
- 集客力(23)
- 雑談(1)
- 顧客目線(1)
- 飲食店×ネットショップコラム(5)
- 飲食店行脚(2)