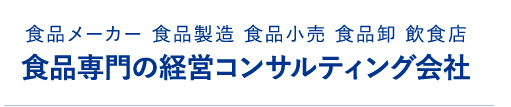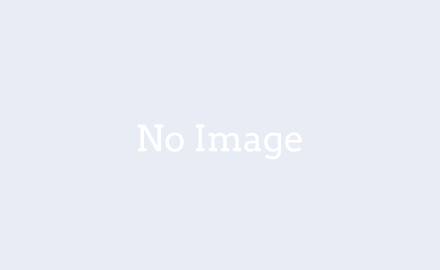2025.03.18UP
【精肉店の勝ち残り戦略】精肉店の弁当デリバリー戦略!値付けは?必要な許認可は?|食肉業界専門経営コンサルタントのブログ(2025.03.18)
目次
精肉店の未来は明るい!ただし時流への適応努力が必要!
近年、「外食よりも手軽で、スーパーの総菜よりも特別感がある」 という理由で、精肉店の焼肉弁当 に注目が集まっています。
「お肉屋さんが作るお弁当なら、美味しいに決まっている!」と期待する消費者が増えており、実際にデリバリーやテイクアウト弁当の売上が好調な精肉店 も多く見られます。
しかし、量販店や大手チェーン店が低価格帯のお弁当を展開する中、精肉店の強みを活かした差別化が不可欠 です。
本日は、「精肉店が成功するお弁当デリバリー戦略」 について、以下の3つのポイントを軸に解説します。
✅ 量販店・チェーン店と差別化する「精肉店の焼肉弁当」
✅ 目安の単価・原価について
✅ 必要な許認可についての注意点
量販店・チェーン店と差別化する「精肉店の焼肉弁当」
🔹 スーパーの総菜弁当・牛丼チェーンとの差別化が必須
スーパーの総菜コーナーや牛丼チェーンの弁当は、「安さ」や「手軽さ」が武器 ですが、精肉店が価格競争に巻き込まれると採算が合いません。そこで、以下のような「プレミアム感」「専門店ならではのこだわり」を前面に押し出すことが重要です。
✅ 差別化ポイント①:肉質の良さを明示する
- 「A5ランク和牛使用」や「店主厳選の黒毛和牛」といったブランドを明示
- 量販店のお弁当との差をつけるため、「肉の厚み」や「部位」にこだわる
✅ 差別化ポイント②:焼き方・タレへのこだわりを打ち出す
- 炭火焼き or 低温調理 で、スーパーの「加熱済み焼肉」との違いを強調
- 「秘伝のタレ」や「手作り薬味」など、付加価値のある要素を追加
✅ 差別化ポイント③:選べるカスタマイズ性をつける
- ご飯の量を「大盛り・小盛り」で選べるようにする
- 肉の部位を選べるオプションを用意(カルビ・ロース・赤身など)]
目安の単価・原価について
📌 価格設定の基本
価格競争に巻き込まれず、適正な利益を確保するためには、「客単価1,000円以上」 を目指しましょう。
専門店の品質とサービスをしっかり盛り込むことができていれば、1,800円~2,500円程度の商品単価を設定しても十分でしょう。
一般的な原価率は 30〜40% が目安となります。
📌価格設定の目安(1食あたりのコスト)
| 弁当種類 | 販売価格(目安) | 原価(目安) | 原価率 |
|---|---|---|---|
| スタンダード焼肉弁当(カルビ&ロース) | 1,200円 | 400円〜500円 | 33〜42% |
| 特選黒毛和牛焼肉弁当 | 2,000円 | 700円〜800円 | 35〜40% |
| ハンバーグ&焼肉コンボ弁当 | 1,500円 | 500円〜600円 | 33〜40% |
| ボリューム満点!ステーキ弁当 | 2,500円 | 800円〜1,000円 | 32〜40% |
📌 ポイント
- 原価率40%以内に抑えつつ、客単価を上げる工夫をする
- 惣菜(副菜)やスープをセットにして、価格のバランスを取る
📌おすすめの原価管理方法
- 精肉店ならではの仕入れルートを活用し、コストを抑える
- 歩留まりを考慮し、「切り落とし肉」や「希少部位」を活用する
- 売れ残りを避けるため、前日までの予約販売を基本とする
精肉店の弁当デリバリーに必要な許認可
📌「通常の精肉販売」とは異なる許認可が必要!
精肉店が弁当販売やデリバリーを行う場合、通常の「食肉販売業」の許可だけでは不十分 です。
「飲食店営業許可」または「そうざい製造業許可」 が必要になります。
📌必要な許認可のポイント
| 許可の種類 | 何をする場合に必要? | 取得方法 |
|---|---|---|
| 飲食店営業許可 | 店内で弁当を調理・提供する | 保健所へ申請、設備要件あり |
| そうざい製造業許可 | 持ち帰り用の弁当・総菜を作る | 保健所へ申請、設備要件あり |
| 食品衛生責任者の配置 | すべての飲食・製造業に必要 | 講習受講で取得可能 |
| 食品表示法の遵守 | パッケージ販売をする場合 | ラベルにアレルギー情報・消費期限を記載 |
📌 注意点
- 店内で弁当を提供するだけなら「飲食店営業許可」でOK
- デリバリー・持ち帰り弁当販売をするなら「そうざい製造業許可」が必要
- ラベル表示義務があるため、食品表示のルールを守ることが必須
もう待ったなしです。今年を変革元年にしましょう。
精肉店が弁当デリバリーで成功するためには、以下のポイントが重要です。
✅ 「専門店ならではの高品質な肉弁当」で差別化を図る
✅ 適正な価格設定(客単価1,000円以上)と、コスト管理を徹底する
✅ 必要な許認可を取得し、法規制を遵守した運営を行う
特に、「事前予約販売」「SNSでのプロモーション」「リピーター施策」 を組み合わせることで、持続的な売上アップが可能になります。
まずは、小規模から始め、「人気メニューを確立する」→「デリバリーエリアを広げる」 という流れで、事業を拡大していきましょう!